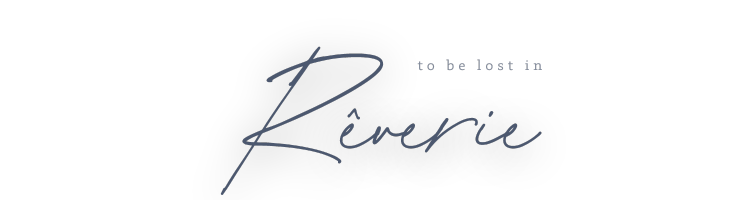どのようなフィクションにおいても、真の純粋さを抱き続ける人間の、社会との不調和が描かれたものが本当に好きだ。この物語に登場する多くの人物たち ── 主人公のテレーザと、彼女と恋に落ちるベルンはもちろんのこと、父親代わりのチェーザレも、環境保護活動家のダンコも、その恋人ジュリアーナも。ベルンの弟分であるトンマーゾだって、それに含めてもいいのかもしれない。
天に焦がれて
十四歳の夏、テレーザは遊びに来ていた父方の祖母の家で、近所に暮らす三人の少年、ニコラ・ベルン・トンマーゾに出会う。ベルンは大変に魅力的な、いわばカリスマ性に満ちた人物で、テレーザは一目で恋に落ちるのだった。物語は、彼女のおよそ二十年にわたって続くベルンへの愛とも執着ともとれる感情と、ベルンの純粋さとその厄介さ(真実の純粋さとは、つねに実に厄介なものだ)が、あらゆる視点から語られていく。
純粋な
こうして書いてみるとありふれた恋物語のようにも思えるけど、彼女らを取り巻く世界は現実の社会とは少しずつ乖離していき、コミュニティを作り生活するマッセリア(イタリアの伝統的な農家・農園を指す)は、理想主義的な登場人物たちの、いわば受け皿のようにもなっていく。
ベルンが信奉し、追求する理想 ── 訳者・飯田亮介氏のあとがきによれば、「宗教的生活、アナーキズム、自然農法、環境保護活動、理想の家族、人間の手が入っていない原初の自然」(580) ── は、多くの人から見れば少なからず異質で、周囲との軋轢をも生じさせる。テレーザは、人びとからのそういった視線すら受け取りつつも、そんな彼を一途に愛そうとする。ただ、ベルンの思想や理想に感銘を受け、共鳴するのとは少し違う形で。
この物語には、大きく分けて二種類の人間が存在しているように思われる。一方はベルンやダンコ、あるいはジュリアーナのような、己の理想に忠実で、ストイックなまでにそれを追求しようと戦う人間。他方でそういった人間たちのどうしようもない純粋さをこそ愛してしまう、テレーザやトンマーゾのような人間。
個人的な話をするならば、私はたとえばベルンやダンコのような人間には幾度か出会ったことがある。そして、彼らのような人間に同調するのではなく、愛することは、とても寂しいことでもある。なぜなら彼らはつねに理想をめざす、つまり「天に焦がれて」いるから。私にではなく。お互い向き合っているのに、なぜか目が合わないような、そんな感覚。この小説を読んでいると、とうに忘れたはずのそのようなもどかしさや切なさが思い起こされた。
滑稽な
そして、そのことがもっともよく描かれるのが第二部。二人暮らしとなったテレーザとベルンは、理想の家族を作ろうと子作りに邁進するが、お互いまだ若く、体に異常もないはずなのに、ふたりが新たな生命を授かることはなぜだかできない。治療に必要な資金繰りのために忌み嫌っていた結婚までして、パーティで募金を呼びかけるというような本末転倒さと滑稽さ。ベルンはのちにこのことを振り返って、トンマーゾにこう語るのだった。
『自分勝手な望みを追いかけたせいで、俺たちはずたずたになっちゃったんだ』
ジョルダーノ,パオロ(2021)『天に焦がれて』(飯田亮介訳)早川書房 pp.380.
それでも、彼はあくまで理想を追うことをやめられない。ベルンがマッセリアを出ていったのちに彼の代わりに荷物を引き取りに来たダンコとテレーザの会話は、次のようなものだ。
「ベルンってやつは、何か大きな目標を追求するために生まれてきた男なんだ」
同上, pp.334-335
やがて彼は言った。
「俺たちにそんなあいつを邪魔する権利はないんだよ」
「わたしが彼の邪魔をしたっていうの?」
(中略)
彼はわたしを振り返って、答えた。
「この世には俺たちひとりひとりよりもずっと大切なものがあるんだよ、テレーザ。君はいつだって身勝手な幸福の概念に縛られていたけどな」
ここでいう「身勝手な幸福の概念」とはつまり、愛する人と結婚したいとか独り占めしたいとかそういう個人的なことなのだろうけども、彼らが追求する大きな理想からすれば、それはたしかに大変ちっぽけで醜いものであるのかもしれなかった。結局のところベルンは、「人間の手の入っていない原初の自然」を求めて行ったアイスランドの洞窟に閉じ込められてしまい、命を落とすことになる。同行していたジュリアーナと、ベルンを死なせたくないテレーザの会話はひどく印象的だった。
「でも、どうしてあそこから引っ張り出せないの?」
同上, pp.522-523
「ほかの誰にもあの割れ目に入る技術がないから。仮に入れたとしても、救助のしようがないと思う」
「岩を壊して、穴を開ければいいじゃない?」
彼女の瞳が熱を帯びた。「この洞窟は保護指定されているの」
「でもベルンが中にいるのよ!」
するとジュリアーナは片手をこちらの頬に置いた。冷たく乾いた手だった。
「あなたには絶対わからないんでしょうね。違う?」
ダンコのいう、「俺たちひとりひとりよりもずっと大切なもの」とは何だろう? きっとそれは、「宗教的生活、アナーキズム、自然農法、環境保護活動、理想の家族、人間の手が入っていない原初の自然」、これらいずれかのことであり、またはこれらすべてのことであり、あるいはもちろん、このうちのどれでもない。この世界には、それがわかる人と、わからない人がいる。テレーザには、わからない。たとえわかっていたのだとしても、それが愛する人の死を意味するのなら、わかりたくなどないのだった。
けれどベルンの真実は、テレーザが見た彼の真実は、決してダンコやジュリアーナ、トンマーゾの語るそれだけに定義されるものでもありえない。もちろん私の書いたひどく大雑把な分類なんて、完全に的外れですらありうる。テレーザは、最後にそのことに気がつくのだった。
この小説は、一人の人間の人生が持つ多面性や奥行きを、幾人かの人物の語りによって描きながら、それでもあるたった一つの真実に辿りつこうとする。だからこそ、この小説のエピローグはひどく美しい。
多くの過ちを犯しながら、それでもベルンがテレーザにささげたもの。テレーザがベルンにささげたもの。あまりにもまっすぐにしか生きられなかった罪深き人間への、あまりにも優しい鎮魂歌のような小説だった。
(2022.09.02)