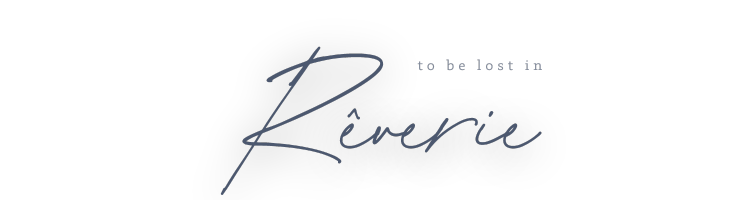わからないこと。放射能、つまりは未知について考えるということ。映画にも、小説にもなっていないことについて語る困難と混乱。彼らにはじめて訪れた永遠がチェルノブイリであったということ。全体主義の中にある自己犠牲についてどうとらえるかということ。それは洗脳なのか、あるいは愛なのかということ。
現代に生きる私は、すでにそれを知っているにもかかわらず、どこかでずっとそれを封印してもきたのだとも思う。わからないふりをしてきたのだと。もうすでに解決済みのことだとでもいうように。
チェルノブイリの祈り ── 未来の物語
自己犠牲をとらえる。
第二章「万物の霊長」のなかのロケット技師によって語られるのは、多くの人びとがみずから志願をして、命をも犠牲に危険な作業にあたったということだった。彼らにはお金が与えられたが、この語り手は、そうした自己犠牲の人びとの目的が決してお金や物品ではなかったと強く訴える。
ぼくはここである男と議論したんです。彼はぼくをこう説きふせようとした。「自分を犠牲にする人間は、自分が、二度とあらわれることのない唯一無二の個だということを感じていない。役割にあこがれているんだ。以前、彼はせりふのない端役だった。筋書きを持たず、背景をつとめていた。ところが、ここで彼はとつぜん主役になった。(…)その死は大きな価値があるんだ、死とひきかえに永遠を手に入れるんだから」。ぼくは同意しない。ぜったいに同意するもんか!
スベトラーナ・アレクシエービッチ(2011)『チェルノブイリの祈り──未来の物語』岩波書店(pp.148-149)
彼と議論したというこの男の分析は、たしかにうなずける部分もある。むろん、彼らの死を崇高なものとして美化して語るには、日本という国の歴史を重ねあわせてみても ── みればこそ、難しいものがある。けれども、それでもやはり私もこの語り手と同じ立場になれば「同意しない」だろうと思う。絶対に。
一方で事故直後の十年前を回想しながら、すぐに帰国の準備に取り掛かった「ヒステリー」で「臆病者」なドイツ人たちにくらべて「ロシア男児」を、「死にものぐるいで原子炉と闘っている。自分の命が惜しくてぶるぶる震えるもんですか!」と感じたように語る女性は、その直後にこんなことをいう。
でも、これもやはり一種の無知なんです、自分の身に危険を感じないということは。私たちはいつも〈われわれ〉といい〈私〉とはいわなかった。〈われわれはソビエト的ヒロイズムを示そう〉、〈われわれはソビエト人の性格を示そう〉。全世界に! でも、これは〈私〉よ!〈私〉は死にたくない、〈私〉はこわい。チェルノブイリのあと、私たちは〈私〉を語ることを学びはじめたのです、自然に。
同上 pp.252-253
先述の男性のいうこととはまた矛盾しているようでありながら、それでもこのこともまた真実だ。けれども彼女はこんなふうにもいう。
(前略)私は党員ではありませんでしたが、やはり、ソビエト人なのです。「同志諸君、躍動に踊らされないでください!」とテレビが夜も昼もがなりたてると、疑いは消えていくのです。
同上 pp.253
耳を傾けるということ
一人の人間の中の揺れ動きや矛盾した感情。一つの出来事をともに経験した人びとの中にももちろん異なる感覚と信じるべきものがあり、また、それらがまったく論理的に配置されているわけではない。歴史や政治や国家の物語にうもれ、おおい隠された個人が、その誰かをどんなに愛したかを語る時、そこからはどんなものが見えてくるのだろう?
かの有名な同じ著者の作品『戦争は女の顔をしていない』にも通じることだけれども、アレクシエービッチが聞き取るのは、外側から確認できる事実ではなかった。そうではなく、彼女はその人の内側、つまり内面において何が起きたのかを聞き取ろうとする。それは事実とは違うけれど、もちろん真実である。目には見えなくて、でもすべての人が持っているもの。彼女は、事実とは異なる語り、現実では即刻切り捨てられるもの、つまり矛盾したものや感情的なものをも真実として受け止める力を持っているのだと思う。だから彼女の本は、こんなにも多くの声で溢れている。私たちはこれを文学と呼ばずに、いったい何を文学と呼ぶのだろう?
原発の消火活動にあたった夫の死をみとった女性の言葉も、記憶に留めておきたい。彼女の話を、私たちはチェルノブイリの悲劇についての話であり、あまりにも悲惨な死についての語りだということもできる。けれども彼女は、だからこそこう語るのかもしれません。
私たちが体験したことや、死については、人々は耳を傾けるのをいやがる。恐ろしいことについては。でも……、私があなたにお話したのは愛について。私がどんなに愛していたか、お話ししたんです。
同上 pp.28
(不明)