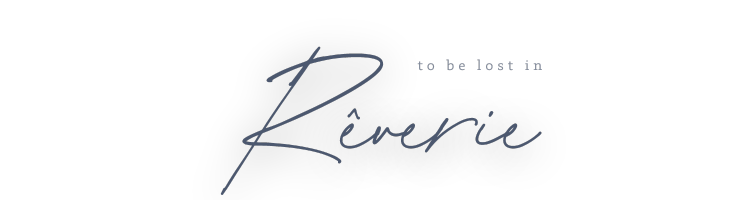希望について、よく考えることがある。それか、「救い」とか。
多くのひとは、なぜかそれが当然あるものみたいに、あるいは当然あるべきものみたいに話すことがあって、捻くれ者の私はたびたび、何か退屈な、悔しいような思いに駆られることがある。
ひこうき雲
全八篇からなる短編集で、それぞれに貧困や消費社会、マルチ商法、都市再開発などの厳しい現実を読み取ることができるが、優しく繊細な筆致のおかげか、読後感はまったく苦しいものではなかった。
希望の物語
『水中のゴリアテ』は、物語の中に直接的に希望が描きこまれるわけではないけれども、なぜかとても光に満ちたラストだ。
タワークレーン上でストライキをしていた父が不可解な死を遂げたのち、語り手の少年が住む土地には一ヶ月以上も雨が降りつづく。電気も水道もとまった家で、持病のある母まで亡くした少年は、手作りの舟に母の遺体をのせて村からの脱出をはかる。どれだけ行っても誰もいない、助けも来ない、水も食糧もないという絶望的な状況で、それでも彼が呼び起こした父との記憶は、たしかに彼の力になっている。
タイトルにある「ゴリアテ」とは、旧約聖書に登場する巨人兵のことだと思うけど、物語の中においていったいどんなことを意味するのだろう?
ゴリアテに唯一立ち向かった羊飼いの少年は、武器もなしにその巨体に勝利するのだ。一方でこの小説は、そのような勇猛さをほとんど持たず、英雄譚とはほど遠い。けれども主人公の少年は、政治や権力や貧困、災害といった大きな運命に翻弄され、すべてが雨に飲み込まれた世界で、それでも一人飲み込まれずに生きている。救済も審判もない終末後の世界に取り残され、今はひとりぼっちでも、いつか「誰か来るだろう」と思える。それはきっと、たしかに希望と呼ばれるべきものかもしれない。
救いがないという救済
苦しい現実の中で、助けを求めて掴んだ手がどうしようもなく誰かを傷つけてしまうことがある。
かつて憧れた男性の頼みで災難に巻き込まれる『そっちの夏はどう?』や、マルチ商法の世界に飛び込み、失意の中にいる女性の心情を手紙形式で綴った『三十歳』をはじめとして、大親友と旅行に行ったはいいものの、些細な感情の絡れが決定的な断絶へと向かっていく様子を描いた『ホテル ネアックター』はこの八篇の中でとてもお気に入りの小説になった。
こういった物語を読んでいると、〈救いがない〉ということが〈救いになる〉という小説の不思議に感嘆せざるをえない。
一筋縄ではいかない人間関係も、大切にすべき人を傷つけ、追い込んでしまったという後悔も、すべては大団円の中におさまって仕舞えば、どうにもならない現実に傷ついた〈私〉はどこにも存在しないことになってしまう。けれど、彼女の書く小説の中にはたしかに〈私〉がいる。私と同じ、どうやっても上手くいかなかった、傷ついた心の手触りがある。そのことこそが、文学による救いなのだと、つくづく思う。
文章はたいへん美しく繊細で、多様な人びとの生活や心情の、本当に細部にまで分け入っていく。私は韓国語については明るくないけど、この作家の翻訳はかなり骨の折れる作業なんじゃないだろうか。けれどもまったく違和感のない、むしろうっとりするような文章だった。日本とはまったく違った歴史と文化を持つ国の人物にこんなにも感情移入できることに驚かずにはいられない。
冒頭でも書いたとおり、この短編集の中にあるのは決して優しくも美しくもない現実だ。それでもその苦しい現実を切り取り、その渦中にいる人びとの感情を掬い取ろうとする行為そのものにこそ、優しさと希望を感じるのもまた、事実なのだった。
(2022.09.02)