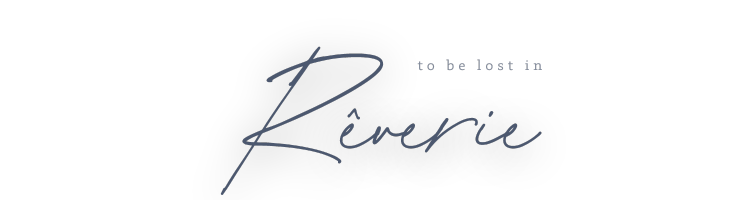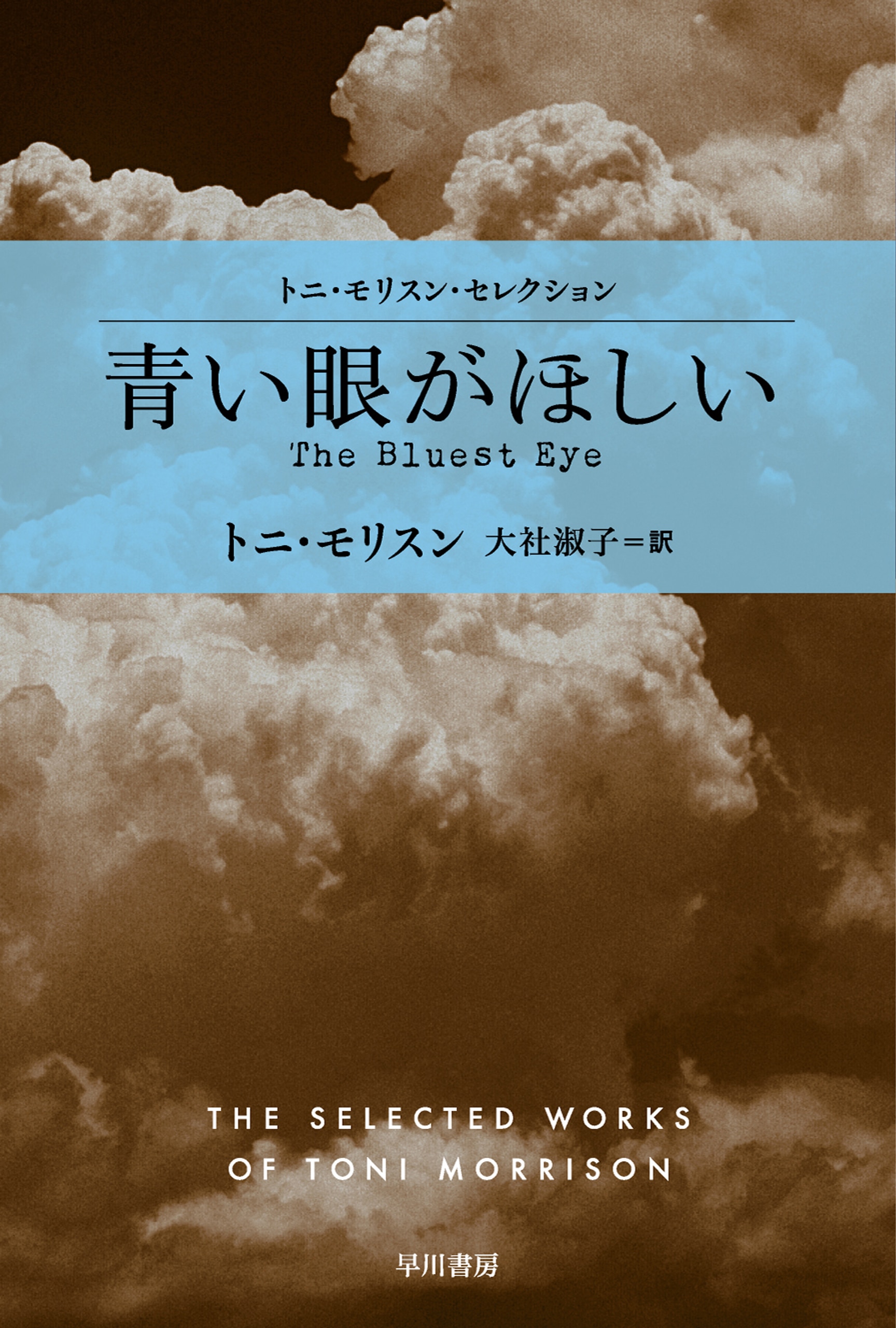本を読んだり読み返したり、 自分なりにあれこれ文章を書いたりしていると、 色んな面白いものを見ることができる。 自分の内面の醜くて臆病な部分、 まあ悪くはないと感じる部分、 本当の願い、 日常的な考えの中にめまぐるしく覆い隠されてしまう真実めいた嘘、 過去からの予知夢、 などなど。
けれどもっとも単純なのは、 自分自身がどんな文章や表現に影響を受け、 ほとんど無意識にそれを取り入れてきたのかということ。
何かについて書こうとするとき、 あるいは書いたあと、 とある表現がぱっと頭の水面に浮かびあがることがあって、 そんなとき私は、 自分がいかに安っぽい模造品であるかという事実について知る。
たとえばもう二ヶ月以上まえのことになるけれど、 私はこんな手紙を文通の相手に送りつけたことがあった。 たった二ヶ月まえの文章なのに、 記憶していたより拙くて簡易だ。
私はこの日の手紙で、 この世界という 〈絵〉 から私の存在を消してしまいたいという願望と、それへの諦めについて語っているけど、 じっさい私はこの手紙を書きながら、 ずっといくつかの小説について考えていたのだった。
それで、 これを書き終わってすぐに私は、 そのいくつかの小説について多くのひとに紹介したい気分にもなった。 もともと自分の頭の中をぱかっと開いてその中身を見せびらかすのが好きだし、 またそうすれば、 私の拙い文章には共感できなかった文通相手の誰かが、 本当に愛すべき文章に出会えるのじゃないかと思って。
トニ ・ モリスン 『青い眼がほしい』
ひとつめは、 ノーベル文学賞受賞作家 (黒人作家として初めて!) のトニ ・ モリスンのデビュー作で代表作ともいえる小説、 『青い眼がほしい』。
この小説の主人公は、 十一歳の黒人少女、 ピコーラ。 彼女は周囲の偏見にさらされ、 いじめられて、 家庭内では暴力を受け、 そしてそれらはすべて自分の容姿が醜いせいだと考えるようになる。 彼女は白人の容姿の象徴でもある 「青い眼」 に執着するようになり、 次第に空想の中へと埋没してゆく。 そんなピコーラの姿を、 時折同じく黒人の少女 ・ クローディアの視点から、 彼女自身とは対照的に描いている点が印象的な小説だった。
さて、 この小説の中にはこんな表現がある。 序盤でピコーラの両親が朝から 「すさまじい喧嘩」(60) をはじめる場面。 ピコーラは息を詰めて 「深く、持続的」(65) な苦痛に耐えている。 夫婦の戦いは熱を帯びる。 静まる。 やっと一息つけるというところで、 かわいそうなピコーラは、 神様に自分を消してくれるよう願う。 すると、 たちまち彼女の身体は消えてしまう。
[…]胃は消えようとしない。 しかし、 それもとうとう消えた。 それから、 胸と、 首も。 顔も消えにくい。 でも、 ほとんど消えた。 ほとんど。 ただ、 きつく、 きつく閉じた眼は残った。 眼はいつも残るのだ。
トニ・モリスン(2001)『青い眼がほしい』(大杜淑子)早川書房(p.67)
ピコーラの忍耐から、 全身を包み込むような痛みと逃げ場のない劣等感がありありと伝わってくる表現。 読んでいるこちらまでもが、 息を詰めて彼女の運命の内側につい入り込む。
ところで私はこの小説のこの部分を読んだ時、 ちょっと驚いた。 初めて読んだ小説だったのに、 読んだ覚えがあったから。
西加奈子『あおい』
というわけで、 次に紹介するのが西加奈子のデビュー作 『あおい』。
三歳年下の恋人「カザマくん」と同棲中の「あたし」(=さっちゃん)は、 ある日自分が彼の子供を妊娠していることを知る。 勤め先のスナックをママとのいざこざで辞めてしまった彼女は迷いの中、 長野のペンションでのアルバイトに応募するものの、 けっきょくはそこからも逃げ出すことになる。
一ヶ月分の荷物を入れていた鞄が壊れ、 深夜の山中で半ば自棄を起こしたさっちゃんはついに地面に寝転んでしまうのだが、 そこで彼女はあることをはじめるのだった。 それが、 「自分の体が消えるところを想像」(112) すること。 これは、 さっちゃんの 「得意技」(〃)だ。
[…]体と同時進行で両腕も、もう二の腕まで消えていて、さて、そろそろ最大の難関の顔だ。顔は、 自分の意識が一番集まっているのか、 いつも消すのに失敗する。 […]
西加奈子(2004)『あおい』小学館(pp.112-113)
初めてモリスンの『青い眼がほしい』を読んだとき、私はこれら小説の類似が好きだった。といっても、自分の身体が消えゆくのをこと細かに想像する、という点だけが似ているのであって、この二つの物語はまったくの別物だ。表面的なストーリー展開としては救いのない前者は、ピコーラの深い自己嫌悪に対し聡明で鋭い憐れみを向けるが、 『あおい』のこの語りは、主人公の内なる生命力を描出しようとする。
『あおい』 が 『青い眼』 を意識的にオマージュしているのか、 それとも偶然の一致なのかはわからないけれど、 この二つの小説の表現が私にとっては強く印象的で、 それが先の手紙ではあんな文章を書きたくさせたのかもしれない。
それにしても、 人というのはあんがい簡単に消えてしまうものだと思う。 なぜだろう? これら小説の主人公たちは消えゆく身体を自ら想像しているものの、 その背景にはある他者からの暴力──それが個人的なものにせよ、 社会的なものにせよ──が存在していることは明らかだ。 人はすぐ消えてしまう。 たとえ物理的に物理的に殺したり、 燃やしたり、 土に埋めたりしなくても。
そういえば、
トーベ ・ ヤンソン 「目に見えない子」 (『ムーミン谷の仲間たち』 より)
トーベ ・ ヤンソンの有名な童話 〈ムーミン ・ シリーズ〉 に登場するキャラクター、 ニンニもそのひとりだった。
ニンニは、 彼女を世話する皮肉屋のおばさんから散々いじめられて、 ついに姿が見えなくなってしまう。 おばさんにニンニを押し付けられた 「おしゃまさん」(トゥーティッキ) は彼女に同情し、 ムーミン一家を頼って彼らのもとへ連れてくる。
「あなたたちもごぞんじのとおり、 人はあんまりいく度もおどかされると、 ときによって、 すがたが見えなくなっちまうわね。 そうじゃない?」
トーベ・ヤンソン(2011)『新装版 ムーミン谷の仲間たち』(山室静)講談社(p.164)
おしゃまさんのいうように、 たしかに人はそうやって消えてしまう。 ニンニの絵は、ない頭の上にふわっとリボンがのっかっていて可愛いけれど、 それ以上にずっともの寂しい。 ニンニが姿を消した背景にあるものも、 やっぱりひとつの暴力だ。
では、 暴力以外でもし人が消えてしまうとしたら、 それはいったいどんな理由だろう?
というのも、 私の私による空想が暴力によるものなのかどうか、 私にはまだあまりよくわかっていないので、 よく検討してみる必要がある。 ニンニがどのように自分の姿を取り戻したのかは本書を読んでもらうこととして、 次は韓国のヤングアダルト小説を紹介してみたい。
ペク ・ オニュ 『ユ ・ ウォン』
この小説の主人公にはちょっと特殊な事情がある。 彼女は有名人で、 誰もが彼女をただ彼女としては見ない。
十八歳のウォンは、 十二年前に起きた大きな火災事故から奇跡的に生還したことで、 人々からの悪気のない (だからこそ、 時として残酷な) 視線に晒されている。
しかも彼女の生還の影には、 二人の 〈英雄〉 の犠牲があった。 その存在が今なおウォンを苦しめる。
一人はウォンの実の姉で、 マンションの十一階から布団にくるんだ妹を投げ落とした。 そしtもう一人は、 それを地上で受け止めることになった通りがかりの 「おじさん」。 姉はけっきょくその火事によって命を落とし、 布団に包まれた幼な子を受け止めたおじさんは足に障害を負い、 時折ウォンの両親にお金を無心しに訪ねてくる。
私は書店で本を買うときには、 冒頭だけを読んで購入を決めることはないけれど (冒頭は本の中で最もキャッチーで、 美しく、 興味深く書かれている場所だから)、 この本は例外だった。 この物語は、 ウォンが朝目を覚ましてリビングへ向かい、 母に抱きつくところからはじまる。 ウォンは日頃から母の態度について 「釈然としない」(6) ものを感じている。
母はよく、私のことを仔猫みたいだと言う。極端に足音がしないのだと、いるならいるとわかるように歩いてちょうだいと、口癖のように言われるものの、歩き方はそう簡単には変えられない。
ペク・オニュ(2022)『ユ・ウォン』(吉原育子)祥伝社(p.6)
私がこれを読んで購入を決めたのは、 じつは私もよく両親にこんなことを言われていたから。 「いるならいるといってくれ」。 母曰く、 私にはあまりにも存在感というものがないらしい。
ウォンの環境を考えるに、 彼女が 「いるならいるとわかるように」 歩けないのは、 もちろん暴力のせいではなくて、 むしろその逆。 善意のせいだし、 だから罪の意識に苦しめられている。
小説は、 こういった状況から周囲に心を閉ざしたウォンが、 自分自身とは反対に堂々と自分を表現するスヒョンとの出会いと交流を通し、 少しずつ自らの人生を取り戻していく姿を描く。
さすがにウォンほどの事情を持つ人は稀だと思うけれど、 程度の差こそあれ、 時として人は自分の存在に罪の意識を持つものだと思う。 とりわけ思春期は、 所属する集団の中での自分の存在意義に敏感になる頃だし、 人はその中で自己を確立していきたいとも願うようになる。
そういう意味ではこの小説は、 いっけん特別な事情を描きながらも、 本質的には人間の普遍的な部分を捉えているのかもしれない。
チョン ・ ソヨン 「雨上がり」 (『となりのヨンヒさん』より)
最後に、 チョン ・ ソヨンによるSF短編集 『となりのヨンヒさん』 に収録されている 「雨上がり」 を紹介したい。
どうして人は消えてしまうのかという視点から考えればこの短編は、 これまで紹介した四つの作品とは少しばかり異なっている。 語り手はこちらも高校生の女の子で、 名前はホン ・ ジヨン。
けれどジヨンの周囲の人々は、 彼女の名前を覚えることができない。 伝えてもすぐに忘れられてしまう。 学校の先生も、 クラスメイトも、 家族でさえ彼女をいないもののように扱う。
今よりもっとたくさんの希望を持っていた時があった。 私が他の人たちの記憶に残ることを、[…]願った時があった。[…]どこであれ、 相手が誰であれ、 私がもう少しはっきり見えることを願った時期があった。[…]自分の存在感が希薄なことに、 せめて何かもっともらしい理由があることを望んだことがあった。[…]
チョン・ソヨン(2019)『となりのヨンヒさん』(吉川凪)p.140
ジヨンが周囲の人びとから見えていないことに、 「もっともらしい理由」はない。 この小説は後半、ジヨンによる一人称の語りから三人称の語りに変化するのだが、彼女が消えてしまう理由は、たしかにそこで明かされはする。 でもそれはいわば”SF的”なのであって、 けっして現実的なものとはちがう。 だから、 ここには読者が自由にその理由を想像したり、自分自身を投影できる余地があるし、 あるいは本当に人が消えてしまうのに「もっともらしい理由」などないと考えてみることもできる。 そういう余白の在り方が、 私にとってはこの短編の魅力だった。
さて、こうして着地点も決めずにつらつらと物事を書いていると、またしても自分の中の見たくもない歪みが見えてきてしまい、きまりが悪い。
ともあれ、これらの小説は何らかの原因でこの世界から消えてしまった人や消えかかっている人、あるいは消えたい人、消えたくても消えられない人、消えたくないから消えたい人、そんなすべての人びとに有用です。よければ、ぜひ。