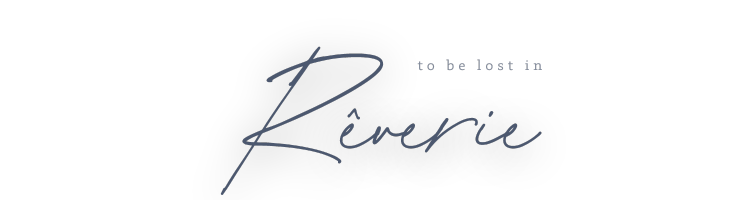自分ではどうすることもできなかった痛みや怒り。罪悪感や無力感。恐怖と不安。
一人はそれを、ただ自らのせいにして。一人は、酔って正気を失うことで。そして一人は、誰にも届かない、届けたくない叫びを孤独に処理することで。
ずっとやり過ごそうとしている。それはつまり、必死に生きようとしてるってことだ。
そのことを、いったい誰が咎められるというのだろう? 指摘し、助言し、救済できるだろう? どうすれば、いつになれば、どれだけこの痛みをやり過ごせば、私たちはあの安らかな天国へと辿りつけるのだろう?
三姉妹
クレイジー女たち
映画『三姉妹』は、「クレイジー女たち」、すなわちある狂った姉妹の物語だった。
長女のヒスクは、夫や娘にどれだけ酷い扱いを受けても、まるで自分が悪いかのように謝って、卑屈に笑ってばかりいる。そんな彼女の娘への愛はどこか滑稽で、ひどく的外れだ。
三女のミオクは、浴びるようにお酒を飲んでは夫や姉に電話でしつこく絡んだり、怒鳴ったり暴れたり。夫の連れ子に良くしてあげたい気持ちはあれど空回っては、周囲を困らせてばかりいる。
そして次女のミヨンは、子どもたちに自らの信仰を強要することで、とても深くて大きな傷を与えている。夫にも不倫されて、側からみれば完璧で幸福な家庭は、今にも崩れ落ちそうなほどに危うい。
こんな三姉妹の息苦しくて不器用で、被害的かつ加害的な日常が淡々と描かれて、そしてだからこそ、どこかユーモアすら感じてしまうような、不思議な映画だった。
緑の灯
韓国でつくられた映画やドラマを見ていると、「家族(といったん見なされたもの)同士の絆や支え合い、愛情はとても大切なものである」という道徳観や倫理観を、日本のそれよりも強く感じることが多い。
ただそういった観念は、作品内に「家族は大切だ」というメッセージや教訓の形、つまりはその観念を、見ている人間に教示する形で現れるのではなくて、むしろ高い理想と、そうはできない現実との乖離として現れているような気がしてならないのだけど、どうだろう?
ようするに私は、「家族や人は支え合うものだ、その絆は何より大切だ」などといったような高い理想があるからこそ、そうはできない現実の状況を何よりも悔しく、嘆かわしく思う気持ちに共感して、韓国で作られた物語を愛してしまうのかな、と思っているわけ。
美しい韓国の言葉や文化がとてもリアルに、あるいは幻想的に綴られた『韓くに文化ノオト ── 美しきことばと暮らしを知る』という本の中では、韓国フィクションを楽しむための「キイワード」として、「ハン(恨)」が挙げられている。
著者は、「恨」は、その字のとおり「「うらみ」の感情」のことだという。そしてその「うらみ」は、白と黒の二種類に分類でき、とりわけ前者、「白いハン」は、日本文化の中からイメージされうるような他者への「うらみ」、つまりは復讐などと言ったような攻撃的な感情とは、些か異なっていると。
「白いハン」は、知られているとおり韓国で強く根付いている儒教の、「性善説によって基礎づけられる」。「性善説」とは、どんな人にも道徳があって、それを磨いて振るえば誰もがこの社会において「上昇」していけるのだという考え方だ。
ところが現実には、人間はそれぞれにさまざまな問題を抱えていて、そのために上昇できずに挫折する。挫折したときの無念の気持ちは人類共通のものであろうが、韓国のような性善説による上昇志向の社会では、原理的にはすべてのひとが上昇可能だと信じられているがゆえに、現実的な挫折に対する無念の気持ちは、ひときわ強いものとなる。つまり原理的には自分も自らが理想とする場所、あこがれの位置に立つことができるが、現実的には挫折してそのような場所に立つことができない無念・悲しみの情、それこそが「白いハン」なのである。
小倉紀蔵(2023)『韓くに文化ノオト』(ちくま文庫) pp.244-245
こんな理論をちょっと援用して当てはめてみれば、この映画全体からはすぐさま、寝具に押し付けて消し去ったはずのあのくぐもった叫び声が、まるですぐそこから、それを眺めている私自身の内から聞こえてくるような感覚が侵入してくる。
まともになりたい。まともになってほしい。幸せになりたい。幸せになってほしい。愛したい。愛されたい。愛したかった。愛されたかった。
そんな願いとはつねに逆行してゆく現実に、無力な他者と自分自分につよく落胆するほかない。そんな悲しみと無念が、つまり「白いハン」が、この作品にはぎゅっと詰まっているように、私には思えるのだった。
まともな女たち
三姉妹(と弟一人)は、〈暴力〉を受けて育った。
映画がはじまれば、つまりひとたび彼女らが動きはじめ、その身体で語りはじめれば、そのことはすぐに想像がつく。彼女らがもう、すでに傷だらけだということが。その傷の痛みと、もうずっと長いあいだ戦ってきた、あまりにも勇敢で、どこまでも〈まともな女〉たちなのだということが。
この映画が絶妙なのは、みな同一の「父」による〈暴力〉に苦しみ、そこから生き延びてきた人間であるにもかかわらず、その痛みへの処し方がまるで違うことがきちんとあらわれていることだ。この映画の主題が、単に虐待されて育った「一人っ子」ではなくて、「三姉妹」であるのは、そのことこそが、この映画の中心にあるものだからだと思う。
姉妹のあいだに差異が生まれるのは、もちろん生まれ持った気質も要因のひとつなのだろうけど、この映画をみるとそれ以上に、〈暴力〉が支配する家庭の中でそのひとがどんな立場にいたのか、ということがとても大きいのかもしれない。
もっとも三姉妹(と弟一人)は、そもそも物理的に暴力を受けていた側と、そうでない側とに分けられる。”わかりやすく”暴力を受けていたのは長女のヒスクと弟であって、次女のミヨンと三女のミオクは、ただ傍観するほかなかった立場にいた。
直接的に暴力を受ける同胞たちを誰よりも近い場所で見ていながら、決してそれを止めることのできなかった無力さと罪悪感、疎外感。
長女のヒスクは幼いころ、暴力の嵐が過ぎ去ったあとは弟を慰めるように抱きしめていた。成長してもなお、彼女は彼を庇う。自分が悪かった、この子を責めないでほしいと。違っていたのは、成長した弟を殴ったのは父ではなく、父の祝いの席を台無しにした彼に怒った次女・ミヨンだったということだ。
ミヨンは、弟と抱き合う傷だらけの姉を、どんな気持ちで見ていたのだろう? その眼差しに、どんな意味があったのだろう? 大人になった彼女の行動の源は、すべてあの幼い日の眼差しの中にあったのじゃないだろうか?
私は、ミヨンのことが少しだけわかる気がした。金銭面で姉を援助しながらも、影では苛立ちや侮蔑や不満を隠しきれない彼女の気持ちが。ほんの少しだけ。
彼女は手を焼かせる妹のことを決して無視しない。父の誕生日祝いの手配だってする。だって、いっしょに天国に行きたかっただろう。 父だけをこの世に残して。母と、姉と、妹と弟と。もちろん子供たちや夫もいっしょに。
それが彼女自身の、たったひとつの大切な願いだったのだろう。それだけを望んで、必死に歩んできたのだろう。それなのにどうして、彼女のそんな姿はほかでもない父親の、あの残酷さと重なりあってしまうんだろう?
過去へと押し戻されながら
三女のミオクが自分の夫に殴りかかったのは、彼が息子に手をあげたからだ。当然、彼女はそのときの夫の中に自らの父親を見ていて ── それでもその時の彼女自身は、あの頃の力を持たない、小さな子供のままだっただろうか? 母の役割を知らず、またその資格がないと言われて泣いた彼女は、戯けることでしか他者に近寄ってゆけない、お酒を飲むことでしか、不安に押し潰れされそうな幼い自分を守ってあげられない彼女とはまったくちがう。だって、彼女はごはんを作ることができる。ほんらい守って、大切にするべき子供を殴った夫に、食ってかかることができるから。
「白いハン」は、「解く」のだという。
人生というのは、どのみちすべて自分の思い通りになるものではない。すべてのひとは、大なり小なり苦しみや挫折を抱えながら生きている。でもその苦しみや挫折を、他者のせいにしたってどうしようもないときに、それは自分の内側に積もってゆくしかない。積もって、ひもの結び目のように結ぼれる。それが、「白いハン」である。だからこの感情は、特定の相手に対する復讐によって解消されるというよりは、いつの日にか結ぼれたこころの結び目を解くことによって、解消されると考える。
同上, pp.243
ミヨンは夫の不倫相手を憎みながら、それでいて彼女の歌に心が動く。子供たちをひどく傷つけながら、それでも娘を抱きしめ、謝ることができる。彼女はまだ、自分自身の本当の願いを言葉にすることができる。胸が強く締め付けられるような、切実な理想主義。ここにあるのは、単なる綺麗事とはまったくちがうのだ。
だからいつの日か、その結び目が解ける日を祈る。それは誰かのためではなくて、私のために。そうすればこそ、初めて私たちは誰かと、あるいは自分自身と、本当の意味で知り合うことができるからだ。映画のラストシーン、三姉妹は、初めて出会ったのだろうか? そのとき初めて、彼女たちは姉妹になったのだろうか? そうでなければ、あの清々しい笑顔はありえない。
だから、いつか出会うその日までさよなら。その日まで、君はただのクレイジー女。
(2023.07.13)