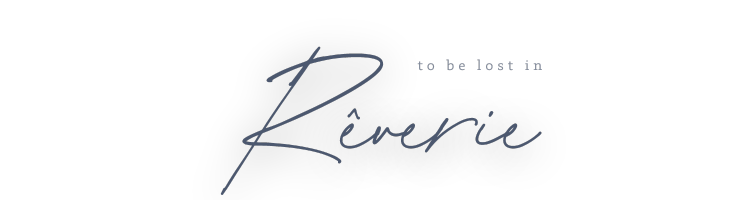二〇二三年がやっと終わりました。
二〇二四年を新たにはじめる前に、去年のうちに読んで好きだなと思った本を、ここに記しておきたいと思います。
韓くに文化ノオト ── 美しきことばと暮らしを知る |小倉紀蔵
2023.03.05 読了。
2000年にちくま新書で出版された『韓国語はじめの一歩』の改題・増補版。
タイトルだけを見れば、韓国語や韓国文化についてとても実用的な情報が得られそうに思われるけれども、「文庫版あとがき」の言葉を借りれば、これらは「看板と内容にあからさまな乖離のある本」(300)だ1。
なんだか、実用的(というのは、たとえば旅行で韓国に行って、市場で品物の値段を尋ねるときにはなんといえばいいか、などの具体的かつすぐに役立つ情報)というよりはとても文学的なエッセイなのだった。この本の文章はとても空想的で、空想的、文学的というのはつまり、現実を超えて真実に行き着こうとする力のことなのだから、私はこの本が好きだ。冒頭は、以下のような文ではじまる。
かつて、汽車に乗って、野の花の咲き乱れる平原の真ん中を走っていたことがあるが、そのときわたしはまだ、生まれていなかった。
小倉紀蔵(2023)『韓くに文化ノオト ── 美しき言葉と文化を知る』筑摩書房 pp.13
この文は著者が、韓国と関係することによって感じる時間感覚や歴史感覚のねじれを表現している。彼はいう。「はじめの一歩から、わたしはすでに歴史を平坦に生きることができない体となってしまったのやもしれぬ。」(18)と。
この年の一月に、『あなたのことが知りたくて 小説集 韓国・フェミニズム・日本』という日韓の作家たちによる短編小説集を読んだ。日本人作家たちの作品を読んでいると、〈日本人である私〉が、〈韓国〉を語るときに否応なく生まれる、とりわけ政治的な罪という躓きに甘んじねばならないことに、どうしても思いが至る。はじめの一歩さえ踏み出せないもどかしさが、どうにもあって。
なぜ私たちは、韓国にかかわろうとするのだろう? なぜ、韓国文化や言葉に魅了されるなどというのだろう? 罪があるのに。あってもなお。
私はそのことについて知りたかった。どうしても。
罪を償うためだろうか? それとも、現在までつづく社会的で政治的な問題を解決するため? あるいはそれらの罪についてまったく無知か、信念上の無頓着であるためというのなら、そのほうがまだ理解しやすい。
この本は、いわば政治的な罪を捉えながらも飛び越えて、あるひとつのエロティシズムに行き着いてしまう。幾度となく、過去に振り戻されつつも。
ディディの傘|ファン・ジョンウン
2023.09.08 読了。
最愛の恋人「dd」を交通事故で失った「d」はあるとき、身の回りすべてのものに体温のような「ぬくみ」を感じることに気がつく。けれども、果たして「もの」が体温を纏うなんてことが、ほんとうにありうるだろうか? 彼はおもう。そんなはずはないと。
すべてのものがこうなるはずはないのだから、変わったのは僕の方だとdは思った。僕が冷たくなった、と。
ファン・ジョンウン(2020)『ディディの傘』「d」(斎藤真理子訳)亜紀書房 kindle版 no.37
この本は、ふたつの中編によって成る。ひとつは今挙げた「d」という物語で、もうひとつは「何も言う必要がない」という、「d」よりはエッセイ風で、語り手と著者の立ち位置が近しい散文。後者の作品の語り手は、お気に入りの食卓で小説を書く。「誰も死なない物語」を完成させようとして。
この本の語り手たちは、なぜかどちらも〈冷たい〉言葉で語らざるを得ないようだ。後者の作家など、小説に「いつもいつも、死んだり、死にかけていたり、死んだように見える人たちが登場」するせいで、「「優しさ」がその小説の助けになるかもしれない」と助言まで受けているくらいだから。
彼らを冷たくするものは、たとえば何?
たとえばそれは、生きているということの取るに足らなさ。生が取るに足らないとはどういうことか。それは諦めであり、絶望であり、孤立のことでしょう。二人から一人。「dd」から「d」へ。見える世界から、見えない世界へ取り残される。「これといった理由がなくてもそうなることはある」。そんな喪失。
私の中の韓国についての記憶でもっとも古いもの、つまり原初にあるものは、人が泣いている姿だった。子供を亡くしたのだったか? 何かの喪失に対し、怒り、嘆き、泣いている姿。テレビ画面の向こう側の姿。同じ画面を見つめていた誰かが言った。「韓国人は大袈裟だからな」と。
私は、「d」の姿に自らを重ねてみる。
(略)彼らとdには同じところがほとんどなかった。他の場所、他の人生、他の死を経験した人たち。彼らは愛する者を失い僕も恋人をなくした。彼らが戦っているということをdは考えた。あの人たちは何に抗っているのだ。取るに足らなさに。取るに足らなさに。取るに足らなさに。
同上 no.1541
私はほんとうに、革命のこととかは、どうだっていい。
連帯とか、革命の中にあっても孤立している人の姿とか。だって私はどうせ透明人間で架空の存在でしかない、私が文学の中に見たいと願うのは、だからつねに真実と永遠だけだ。
この小説のなかに感じる、生命力について考える。物語の続きを探す力について。
それは、誰にも訪れうる普遍的な喪失と、韓国社会に特有のあのうねりの中で共有された痛みと怒りが重なるとき、はじめて立ち現れる力のこと。
物語の語り手は死んだが、それでもなお、その先に続きがあるはずだと、存在しないページを繰ろうとする手。私は今もテレビの画面から目を離すことができない。その手つきがあまりにも純粋で痛々しいから。
あの魚は、彼は、いつ戻るのだろうか? 最愛の人は答える。
あんたが見てないとき。誰も見てないときによ。
同上「なにも言う必要がない」no.1541
この本の中には、単なる絶望でも諦めでも孤立でもない、永遠の、真実の孤独がある。また何よりそのことに発する生命力が。
この本に触れた手が熱い。
私は知らなかった。私は冷たい。
「待つ」ということ|鷲田清一
2023.12.15 読了。
「待たなくてよい社会になった。待つことができない社会になった。」などと書かれると、少し身構えてしまう。だいたいこんな文句の先には社会構造への問題意識があって、そこに埋没する人間への失望があって……
私は、”正解”を言われるのはきらい。
責められてるような気がするからではないし、とうぜん”正論”がきらいだからでもない。
“正解”とはたいてい、人間の生活という戦いを知らない人が独りよがりに押し付ける、役立たずで陳腐な、ただのがらくたに過ぎないからだ。だとすると、この本の”正解”(=「待つ」)を非凡にするのは、そこに向かうまでの、「曲折」や「抗い」に目を向けているところだと思う。
著者の話は精神疾患や認知症患者への支援にまで及ぶのだが2、そこで紹介される「パッチング・ケア」などの例を用いて、「待つ」といういとなみを解きほぐし、再定義してゆく。
この本の中で深く哲学された「待つ」は、いわば”愛”や信頼”とも、また”理解”や受容”とも言い換えが可能だが、著者は、ポール・リクールという人の言葉を引きながらそれも退ける形で、「初発の体験」と「理解」との「あいだ」にあるものに注目している。
ポール・リクールは、何かをほんとうに「理解する」というのは、同化(appropriation=所有、つまりはわがものとすること)ではなく、かならず「貪欲で自己愛的な自我の放棄」、つまりは所有権剥奪(desapproriation)をともなうものだと書いている。これまでなじみのなかった何かを理解したときには、ひとはもう、おのれの軸を移し、自己を理解する新しい地平に入っているのだ、と。そう説いている文章をかつてわたしは好んで引いたものだが、この文脈で再度引くことはとてもできない。そこでは初発の体験と理解という二つの出来事に議論が定位され、そのあいだの抗いの時間は飛び越されているからだ。
鷲田清一(2022)『「待つ」ということ』KADOKAWA pp.98
なにしろ、人は言うものだ。理解し、受容せよと。それが自分自身のことであれ、他人のことであれ。そしてまた、こんなふうに言いもする。仕方がない、と。あなたが理解できなかったのも仕方がないよと。それが、いつも理由も知れず悲しかった。人にそう言われることも、何より私自身が、そのようにしか私の体験を捉えられないことも。そのような議論の中で私はつねに無理解者であり、非寛容者であった。私は、抗っていたのだろうか?
この本を読んだのち、ふと祖母のことを思い出していた。正確には、祖母を〈追いかけていた〉頃のことを。私が十四だか十五だかのときに、私の祖母は認知症を患ったのだが、とつぜん癇癪を起こして、家を出ていってしまうことがたびたび起こったのだった。それは今思えば、彼女の「抗い」の形であったのかもしれない。
祖母を追いかけるのは私の役割だった。祖母を連れ戻すためではない。もちろん、はじめはそのつもりだったが、途中から意味が変わったのだ。七十を超えた老人とは思えないほど早く歩き、とうぜんこちらの差し伸べた手も驚くほどの力で払いのける彼女を、中学生の子供が連れ戻せるはずもない。どんな行動も、声掛けすら無意味だ、「意味」のあるものはすべて。そう気づいたのは、私も散々「抗った」あとだったけど。
だから、私が祖母を追いかけたのは、もちろんそのまま行方不明になってしまわないためだったし、車に轢かれたりしないため、彼女がぶつかったり、無意識に無礼を働いてしまうことになる町の人々に謝ったりするためだった。そして、いつか彼女が私の声の届く世界にふたたび戻ってきたその瞬間を「待つ」」ために。
町内を縦横無尽に歩き回る彼女が、何かに混乱し腹を立てているということだけがわかるのだが、そんな混乱や怒りと隣り合いながら、ただただ時間だけが過ぎていって、日が暮れてゆく。町の人の驚いたような、ぎこちない挨拶を、今でもたまに思い出す。そうして、少しずつ、”戻ってくる”。私はいまだに、夕暮れの時間が好きだ。〈そのとき〉の空の色が好き。
成長して大人になった私は、ある決断をした。二つの選択肢があり、一方を選べば苦しみはつづき、もう一方を選べばきっと後悔することになるだろう、というような決断。私はけっきょく後者を選んで、そしてじっさい、後悔してる。しかし、”後悔”といってもいったい、何を悔やんでるというんだろう? どちらを選んだにせよ、自らが引き受けねばならないものは耐えきれないほど重かったというのに。
待たなかったこと。
著者は、待つことを放棄することからしか、「待つ」ははじまらないという。逆説的だが、それでもそのような放棄もやはり「待つ」へと連続していくことを、「未知の事態へのなんらかの開け」と呼ぶのである。
それは、他者を自己へと同化することではなく、逆に他者の前に自己を差し出すことであり、その意味で、他者との抜き差しならぬ関係にみずからを、傷つくこともいとわずに挿入してゆくということである。
同上 pp.186
〈わたし〉独りが関係の意味を決めるのではない。そういう他者との関係のなかにみずからを据えること、つまりみずからをあえて傷つきやすい存在とすることである。
私は、祖母に大した愛着がなかった。祖母もそうだろう。だからきっと私が選ばれたのだ。本当の意味での「待つ」に到達するまでの抵抗が、もっとも少ないのは私だったから。じっさい、祖母の多少の暴言や暴力というものに、私は自分でも不思議に思うほど、傷つかなかった。私が思うに、対象に対する愛が大きければ大きいほど、「待つ」を放棄するにいたる道のりは、険しくなるものじゃないだろうか。
私は、待てなかった。
私の人生が私だけのものであるという事実は、まったく何の慰めにもならない。むしろそれは、私は、何にも、誰にも待たれることがないという事実すら突きつけるのだから。
私の苦しみは。
これまで、何度もこんな主語を浮かび上がらせては沈黙してきた。私の後悔を、飽きることなく解釈し直そうとして。
この本のいうことは、ただしい。
私の「待つ」がはじまらない。永遠に。